-
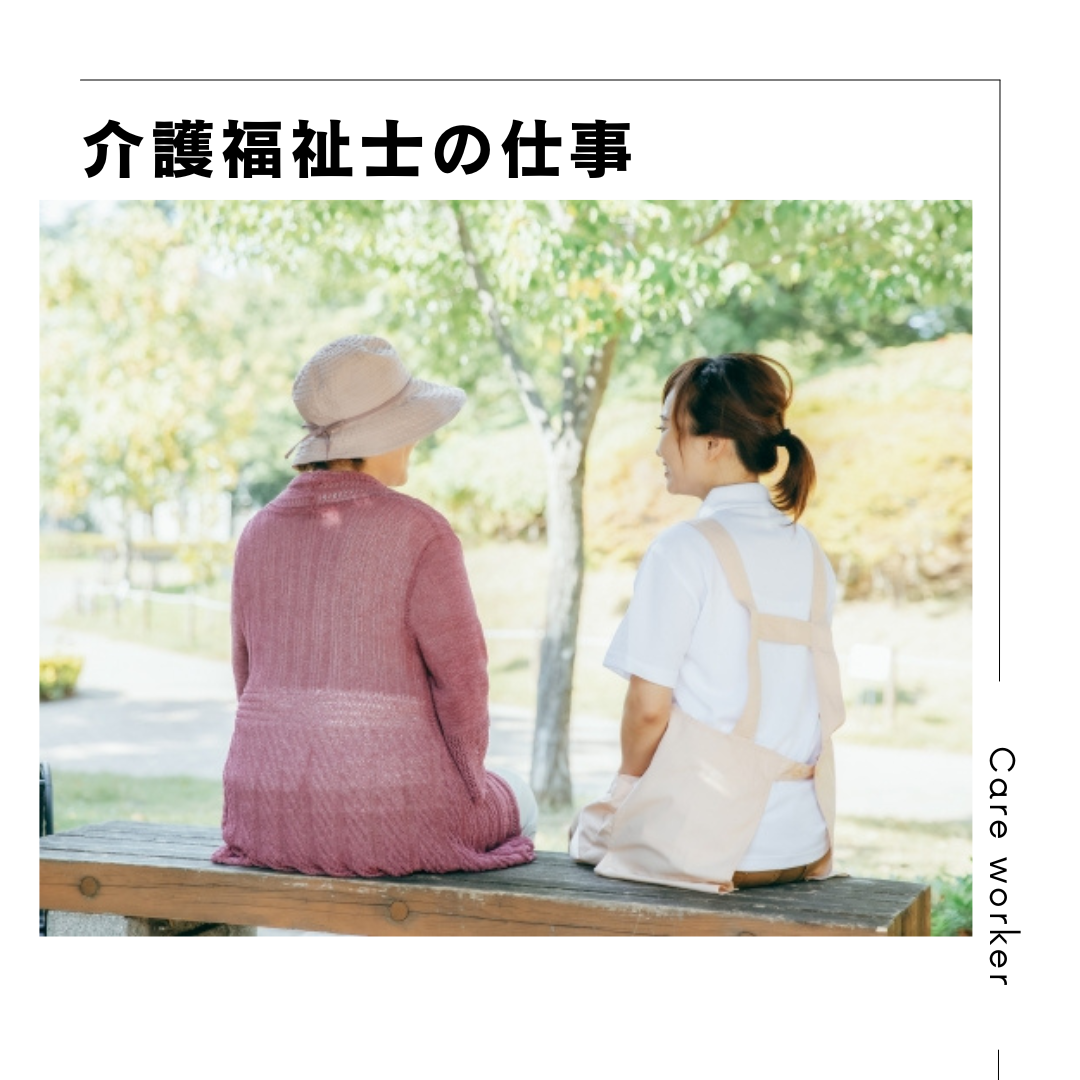 介護福祉士とは? 勤務先・仕事内容・平均年収も紹介
介護福祉士とは? 勤務先・仕事内容・平均年収も紹介介護の技術と専門知識を持ち、介護のスペシャリストとして利用者を介助・支援する介護福祉士。介護施設には様々な種類があり、「どのような施設で働くのが自分に合っているのかな?」と思う方も少なくありません。こ・・・もっと見る
介護職関連資格 介護職の転職 おすすめ情報 -
 すぐに辞めずに続けてよかったです|登録者の声
すぐに辞めずに続けてよかったです|登録者の声Nさん 60代 介護職 登録されたきっかけは? 求人誌を見て家の近くの求人を見つけて電話しました。 自転車でも通える所で興味があったので電話しました。 登録されてみていかがでしたか・・・もっと見る
登録者の声 -
 初めての介護職!将来性や未経験でも働きやすい職場のポイントは?
初めての介護職!将来性や未経験でも働きやすい職場のポイントは?はじめに 子育てで忙しい主婦でも、子どもの成長とともに仕事への興味が出てくるものです。 できれば将来性のある仕事をしたいと考えるなら、介護職が当てはまる可能性があります。 高齢化・・・もっと見る
おすすめ情報 -
 2024年3月分、マイページ会員さま限定!プレゼントキャンペーン当選発表!
2024年3月分、マイページ会員さま限定!プレゼントキャンペーン当選発表!先日ご案内した2024年3月分のマイページ会員さま限定のプレゼントキャンペーンの当選者が決まりました! 厳正なる抽選の結果、下記の4桁番号の方々にプレゼントが当選いたしました! 492・・・もっと見る
ぺんぎんハートクラブ -
 マイページ会員さま限定、ホワイトデー!プレゼントキャンペーン開催!!
マイページ会員さま限定、ホワイトデー!プレゼントキャンペーン開催!!マイページ会員さま限定、ホワイトデー!プレゼントキャンペーン開催!! 先月に続きマイページ会員さま限定のプレゼントキャンペーンを実施します 今回は「ホワイトデー!プレゼントキャンペーン・・・もっと見る
ぺんぎんハートクラブ -
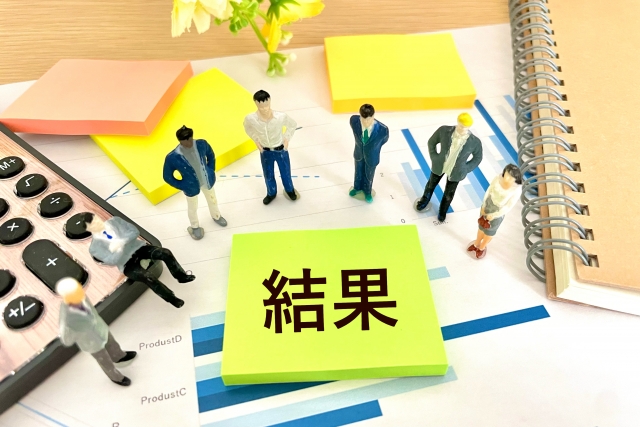 【2024年3月25日更新】 静岡県 第36回介護福祉士国家試験 合格発表速報
【2024年3月25日更新】 静岡県 第36回介護福祉士国家試験 合格発表速報第36回介護福祉士国家試験の筆記試験は、令和6年1月28日に実施されました。 この記事では、2024年3月25日に結果が発表された第36回(2023年度)介護福祉士国家試験の合格率や合格ラインの・・・もっと見る
介護職関連資格 介護職の転職 -
 子どもが大きくなるまで派遣で働きたい|登録者の声
子どもが大きくなるまで派遣で働きたい|登録者の声Sさん 40代 介護職 登録されたきっかけは? 家庭の状況などを考慮して派遣でお仕事を探していました。 webサイトをを色々みていたら、たまたま、家の近くの求人を見つけました。 その仕・・・もっと見る
登録者の声 -
 2024年2月分、マイページ会員さま限定!プレゼントキャンペーン当選発表!
2024年2月分、マイページ会員さま限定!プレゼントキャンペーン当選発表!先日ご案内した2024年2月分のマイページ会員さま限定のプレゼントキャンペーンの当選者が決まりました! 厳正なる抽選の結果、下記の4桁番号の方々にプレゼントが当選いたしました! 325・・・もっと見る
ぺんぎんハートクラブ -
 介護職の処遇改善手当とは?対象となる職員やその支給額について解説します
介護職の処遇改善手当とは?対象となる職員やその支給額について解説しますはじめに 介護職は、身体や認知機能に障害を持つ人々の日常生活を支援する職業であり、肉体的・精神的に大きな負担が伴います。 さらに、高齢化社会が進む中で、介護職に対する社会的な需要が増加・・・もっと見る
介護保険 -
 マイページ会員さま限定、バレンタインデー!プレゼントキャンペーン開催!!
マイページ会員さま限定、バレンタインデー!プレゼントキャンペーン開催!!先月に続きマイページ会員さま限定のプレゼントキャンペーンを実施します 第十弾は「バレンタインデー!プレゼントキャンペーン!!」 毎年恒例のバレンタインデー!最近は義・・・もっと見る
ぺんぎんハートクラブ -
 仕事探しの難しさ|登録者の声
仕事探しの難しさ|登録者の声Mさん 60代 介護職 登録されたきっかけは? 自分の希望する勤務条件、そして年齢もあり、中々希望するような求人が見付からず困っていた時に、DOMOで60歳以上歓迎の求・・・もっと見る
登録者の声 -
 ケアマネ未経験者の転職は厳しい?成功のための押さえるべきポイント!
ケアマネ未経験者の転職は厳しい?成功のための押さえるべきポイント!はじめに 介護の仕事において、利用者の身近で仕事ができ、利用者や家族がよりよいケアを受けるためのプランを作成し実現させていくというケアマネージャーの仕事は非常に魅力的です・・・もっと見る
介護職の転職 -
 人の役に立つ仕事がしたく思い切って介護業界へ転職|登録者の声
人の役に立つ仕事がしたく思い切って介護業界へ転職|登録者の声Nさん 60代 介護職 登録されたきっかけは? 私の母親がコロナ流行の時に病院に入院しました。 当時は感染対策として面会禁止で会う事ができず寄り添って介護することが出・・・もっと見る
登録者の声 -
 年末年始休業のお知らせ
年末年始休業のお知らせ平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊社の年末年始休業は下記の通りとさせていただきます。 休業期間 2023年12月30日(土)~2024年1月3日(火) ・・・もっと見る
お知らせ -
 浜松市区統合に対応しました
浜松市区統合に対応しました2024年1月1日からの浜松市区統合に対応しました。 新しい区名(浜松市中央区・浜名区・天竜区)にて求人情報を検索可能です。 ぜひご利用ください。 [link-job 浜松市中央区の・・・もっと見る
お知らせ -
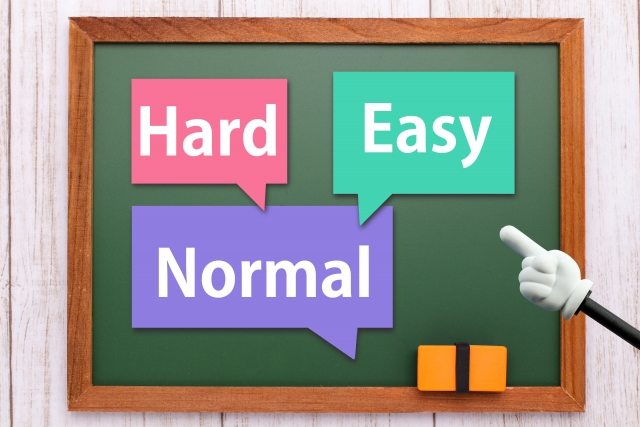 介護福祉士国家試験の難易度は?合格率や合格するために必要なことを解説
介護福祉士国家試験の難易度は?合格率や合格するために必要なことを解説介護福祉士の国家試験は難しい? 介護福祉士として仕事をするには、国家試験に合格しなければなりません。 その際に気になるのが合格率ではないでしょうか? &nbs・・・もっと見る
介護職の転職 -
 2023年11月分、マイページ会員さま限定!プレゼントキャンペーン当選発表!
2023年11月分、マイページ会員さま限定!プレゼントキャンペーン当選発表!先日ご案内した2023年11月分のマイページ会員さま限定のプレゼントキャンペーンの当選者が決まりました! 厳正なる抽選の結果、下記の4桁番号の方々にプレゼントが当選いたしました! 33・・・もっと見る
ぺんぎんハートクラブ -
 介護職としての経験を積んでいます|登録者の声
介護職としての経験を積んでいます|登録者の声Mさん 50代 介護職 登録されたきっかけは? ふじのくに静岡介護求人ナビ」を見ていて興味ある求人を見つけたので問合せをしました。 すぐに返信の連絡があり、担当の方から求人の内容も説・・・もっと見る
登録者の声 -
 パート勤務の介護職必見!もう年収の壁は気にしなくていい?2023年10月から!
パート勤務の介護職必見!もう年収の壁は気にしなくていい?2023年10月から!もう年収の壁は気にしなくていい? 「年収の壁」を気にして勤務しているパート介護職は少なくないでしょう。 扶養内で働く以上、「年収の壁」は意識せずにはいられないも・・・もっと見る
介護職の転職 -
 マイページ会員さま限定、ブラックフライデー!プレゼントキャンペーン開催!!
マイページ会員さま限定、ブラックフライデー!プレゼントキャンペーン開催!!先月に続きマイページ会員さま限定のプレゼントキャンペーンを実施します 第九弾は「ブラックフライデー!プレゼントキャンペーン!!」 最近日本でも聞くようになってきたブラックフライデー。お・・・もっと見る
ぺんぎんハートクラブ
お役立ち情報一覧
232件中1~20件表示



